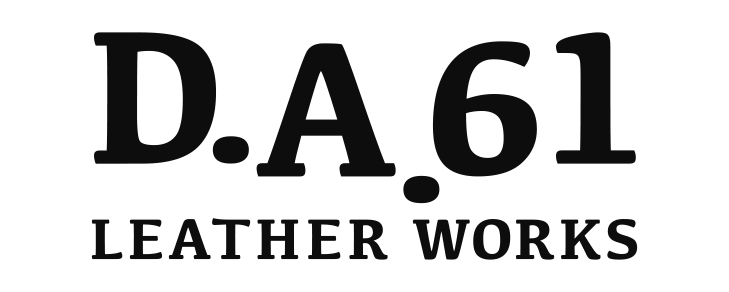すでにご存知の方も多いと思うのですが、念の為。この映画は山岳漫画の「岳 -みんなの山-」でも有名な石塚真一さんの、長編ジャズ漫画の一部を映画化したものです。迫力の音楽が評判のようなので、せっかくなら映画館で観ておこう、と思い立ったのでした。
革作家であるとともに、永年サックスを吹いてきて、現在はサックス講師でもある私なので、ついつい厳しい見方になってしまいそうです。でも、できるだけそうならないように心がけつつ観ました。感じたことは大きくふたつ。「なるほど」と共感すると同時に「これでいいのかな」と心配になる気持ちでした。
まず「なるほど」となったのは、この映画の音楽を担当し、実際に演奏もしているピアニストの上原ひろみさんの存在感、演奏の素晴らしさでした。実際に私の周りでも上原ひろみさんの音楽とその音響に対する称賛の声が高く、その評価にも頷けます。そしてこの映画は若々しさに溢れ、音楽、特にジャズをすることの魅力について、とても分かりやすく、劇中のセリフや映像で表現してくれます。この映画を通じて音楽やジャズ、楽器やバンドに興味を持つ方が少しでも増えれば嬉しいですし、ジャズってなんだかオヤジくさくて難しそう…とか思っている方は是非観てみてください。少し見方が変わるかもしれません。
若者たちがまっすぐな志で困難を乗り越えつつ展開していく熱いストーリーと、劇場のドルビーシステムで威力を増した「スゴイ音」。一気に感動のフィナーレへと包みこまれていくかと思いきや、やがて私の中で「本当にこれでいいのかな」というモヤモヤとした何かが燻り始めました。結局、いまひとつ物語に入り込めぬまま、気がつくと冷静にエンドロールを眺めていたのはなぜなのか、劇場を出たあとも分かりませんでした。
原作の漫画では、当たり前ですが実際に音は鳴りません。読者それぞれの頭の中で主人公たちの熱い演奏が鳴っていたはずで、そうして物語は成立していたわけです。その想像の世界へ果敢にも演奏をつけたところが、この映画の面白いところであり、評価もされるべき部分です。でも、どこか違和感が拭えないでいたのです。
しばらく考えてみましたが、どうやらその理由は、演奏中の映像の過剰な演出にあるような気がしてきました。元は漫画の表現なのだから当たり前と言えば当たり前なのですが、感動を強いられる感じとでもいいましょうか。「不思議な力を得た音が、観衆からはこう見えている。」といった演出はわかりやすいのですが、今は音楽がある以上、あまりに説明が過ぎる。私はそれが受け入れられなかったのだと思います。
音楽への過ぎたるお膳立ては、個人と音楽との接点を狭く小さなものにしてしまうことがあります。頭が先行して、せっかくの目の前の体験を「感動ジャズ」とか「根性ジャズ」みたいにカテゴライズしてしまうかもしれません。作中に登場する時代錯誤のジャズミュージシャンのように、音楽のことをジャズのジャンルでしか語れなくなってしまってはもったいないです。
まるで子供の自主性を心配する親のようでもありますが、サックス講師でもある私が生徒に期待するのは、やはり自由な感性と自由な音です。言葉や演出に惑わされず、できるだけ自分の音で語り、自分の心で聞き、感じて欲しいと願います。
少し話が勝手になりましたが、結局というかやはり、いつのまにか厳しい見方をしてしまったようです。でもこの映画「BLUE GIANT」で伝えようとしていた、「演奏をするということは、嘘偽りのない自分をさらけ出して心を通わせ合うことなのだ」という部分は大いに共感でき、主人公たちのそんな熱い心は、ひしひしと伝わってきました。私ももっと心を燃やして音楽やレザー制作に取り組まねば、と決意を新たにしているのです。
そして、やはりバンドっていいですね。